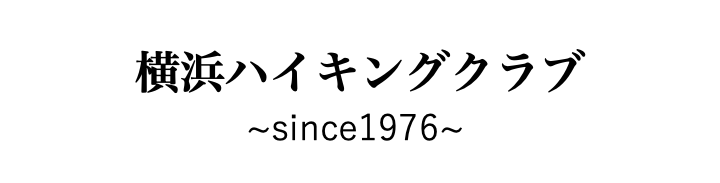巣雲山
<コースタイム> JR宇佐美駅9:00→みかんの花咲く丘コース→富士見展望ひろば10:30→大丸山11:00→巣雲山11:30(山ご飯&ティーtime)→巣雲山13:30(峰コース)→巣雲山登山口14:30-JR宇佐美駅15:30
6月1日、巣雲山に登りました。山頂からの眺めはとても良く、遠くの山々や街並み、相模灘や駿河湾まで見渡せました。富士山は見えませんでしたが、それでも大満足の景色でした。
山頂ではみんなで熱々のキムチ鍋を囲みました。もちもちのお餅と野菜が入っただしの効いたスープは、体にしみわたり、とても美味しかったです。みんなで分け合いながら食べる楽しさもあり、山ご飯の良さを感じました。食後にはコーヒーとカップケーキもいただき、自然の中でのんびり過ごす贅沢な時間を楽しみました。リーダーさん、参加者の皆さん、ありがとうございました。
丹沢主稜縦走(蛭ヶ岳山荘泊)
<コースタイム>(1日目)西丹沢9:10→展望園地11:00→檜洞丸12:45/13:15→金山谷ノ頭14:10→臼ヶ岳15:00→蛭ヶ岳16:45
(山荘泊り) (2日目)蛭ヶ岳山荘6:00→丹沢山7:40/7:55→塔ノ岳9:00→花立山荘9:40→見晴茶屋11:20/11:40→大倉バス停12:30
1泊するなら歩けるだろうか?と初の丹沢主脈縦走に参加。

前日の大雨でゴーラ沢は水かさが増し裸足で渡る人が多い中、石の上をピョンピョンと渡ったところ川の中にズボッと入ってしまい靴下びしょ濡れ状態に…横着な性格が仇になる。檜洞丸までの道のりは長く辛かったが、鮮やかなピンクのつつじと真っ白なシロヤシオが真っ盛り、それに新緑が相まって心を癒されながら歩いた。蛭ヶ岳山頂直下は最後の試練で岩場の急登が続く。鎖場やハシゴを登り山荘にたどり着き、到着して20分ほどで大雨がザーッと降りだしギリギリセーフだった。
蛭ヶ岳山荘は食事がいまいち…という評判だったが、名物蛭カレーは安堵と疲れと空腹の私にとって、人生で一番美味しいカレーだった!!暖かいものがいただけること自体が本当に有難い。楽しみだった夜景・星空・朝焼けは
雲に邪魔され満喫出来なかったが、小屋に飾ってある素晴らしい写真は、また絶対に来よう!という気持ちにさせて
 くれた。二日目は予報に反して小雨がパラパラ降り眺望は全くなかった。ヤビツに降りる予定だったが、天気とバス時間を考慮して塔ノ岳から大倉に下山した。
くれた。二日目は予報に反して小雨がパラパラ降り眺望は全くなかった。ヤビツに降りる予定だったが、天気とバス時間を考慮して塔ノ岳から大倉に下山した。
初めて丹沢を歩いたが、道は綺麗に整備され眺望が良ければアルプス並みの楽しさがあるだろう。空気の澄んだ冬にまたチャレンジしたいと思った。私に合わせて超ゆっくりゆっくり山行にしていただきありがとうございました。
草戸山
<コースタイム> 高尾山口駅(9:35)→草戸峠(11:10)→草戸山(11:20)(昼食)(12:00)→三沢峠(12:35)→泰光寺山(13:05)→西山峠(13:25)→梅の木平バス停(14:50)→TAKAO599MUSEUM(15:20)
夏日を超える気温でしたが、木陰の中を時折風が吹き抜け、気持ちの良い山行でした。多少のアップダウンはありますが、総じて歩きやすく、平日のせいもあってか行き交う人もまばらで、のんびりお喋りしながら歩きました。西山峠のあたりに木彫りのオブジェが二つ、立木を利用したフクロウのトウテムポールと、倒木を利用した龍があり、ユーモラスでした。
ゴールはTAKAO599MUSEUM。ここには鳥獣の剝製や昆虫・植物の標本が美しく展示されていて、まるで精巧な作り物見ている様に錯覚してしまいました。併設のカフェでほっと一息つきました。

日向山・尾白川渓谷
<コースタイム>
1日目:9:45矢立石登山口~10:50 10/5標識~12:00日向山山頂~13:30 10/5標識~14:15矢立石登山口
2日目:6:30尾白川渓谷キャンプ場~7:16三の滝~7:31旭滝~7:57百合ヶ淵~8:36神蛇滝~9:17不動滝~10:37神蛇滝~11:26尾白川渓谷キャンプ場
晴天とはいかなかったが曇り空に時々陽が差し込む、登山で汗ばんだ身体にはちょうど良い気候であった。日向山は白砂が明るく映えたきれいな山頂で、絶壁に見える頂上周辺も思ったより広く、奥まで足を延ばし甲斐駒や鳳凰三山を眺めたり、昼食を取ったりしながら眺望を満喫した。
夕食は、キャンプ場のリバーサイドに陣取り、鍋料理と少しのアルコール(予想外に虫もいなかったので)を堪能しつつ、暗くなるまでリラックスして団らんした。
キャンプ場は歴史を感じる古さで、炊事場は唯一の水場で洗面所も兼ねており、トイレは男女共同であった。バンガロー内にはコンセント1か所と照明1つ、壁の釘を利用して予備の靴紐をつなげて臨時の物干し場を作ったり、工夫を楽しんだ。
翌日の尾白川渓谷は川や滝を横目に見ながらのアップダウンで飽きることがなかった。最奥の滝まで行き、鎖場を上り、天然シャワーを浴びて気分爽快の山行となった。
車を出して運転もして下さったCLに大感謝、皆様ともご一緒できてうれしかったです。大変お世話になりました。
佐原あやめパーク
<コースタイム> 潮来駅9:28→潮来あやめ園9:40→水郷歩き→船宿・出島11:10(お昼)
→さっぱ船乗船12:10~加藤洲十二橋めぐり~13:30佐原あやめパーク・14:00シャトルバス乗車→街並み交流館~小江戸佐原街歩き~佐原駅15:45
今日は、山を歩くと言うより、観光を兼ねた街歩きになりました。しかし、YHCなので歩きます。
茨城県の潮来に来ました。紫、黄色、白に彩られたあやめを堪能しながらあやめ園を抜け、川沿いに歩いていきました。常陸利根川沿いをずっとずっとずっと歩いて、一回りしてやっと出島に着きました。ここでお昼。(ほっ)
お昼をいただいた後は、今日のメインイベントの「さっぱ船」の乗船。船は心地よい速さで進み、風が感じられて爽快です。利根川から支流に入るとき、川の高さが異なるのでその高さを合わせるため小さな水こう門のある場所に入ります。(ここが面白かった。心の声)すれ違い様に向こうの船にワンちゃんがいたりして。川の高さがあったら門が開いて、支流を進んでいきます。加藤洲十二橋をめぐり、女性の「さっちゃん」船頭さんが時折歌を歌ってくださいます。声の美しいこと。楽しいひと時を過ごすことができました。
シャトルバスに乗って、佐原へ向かいます。佐原は、利根川水郷の中継基地として栄えた場所で、現在でも川沿い中心に江戸情緒ある小さい街並みが残っています。伊能忠孝の旧宅を訪れました。伊能は醸造業を営んでいて、土蔵造りの店舗があり、炊事場や書院がありました。地図を作った人で知られていますが、測量を始める前は商人としても才能を発揮したり、天明の飢饉のときに村人を助けたりと佐原で大活躍をした人でした。
お休みどころでしょうゆジェラードを食べ、荒物屋で手作りの竹製品を見て、柏屋の最中をお土産に購入しました。
千葉から横浜までグリーン車に乗り、帰りは宴会をしながら帰りました。あやめ園・さっぱ船・小江戸歩きと
盛り沢山な1日で、企画したCLに感謝、感謝です。



甲州高尾山
<コースタイム> 勝沼ぶどう郷駅8:15→大滝不動尊8:45→展望台9:30→甲州高尾山東峰(昼食)10:30→甲州高尾山11:05→柏尾山12:15→大日影トンネル遊歩道入口13:30→勝沼ぶどう郷駅14:20
勝沼ぶどう郷駅に集合し、タクシーで登山口(大滝不動尊)手前まで移動。この選択が大正解!!CL曰く下見の際は舗装路を延々と2時間近く歩いたそうだ・・・やはり山行下見は大切であると実感した。
展望台までの登りは修験の山?を思わせるよう景色や荘厳な滝を眺めながら、時にはSLの登山豆知識を聞きながら、みんな楽しく登ることができた。参加者の半分近くは高尾山という山名から山頂までも楽しい登りが続くと信じていた・・・が、ここから先はめったにお目にかかれない倒木の嵐という難敵を短い足でまたいだり、スリムなお腹?に気をつけながら倒木の下をくぐったりとアスレチック気分を味わいながらやっとのこと山頂に到着。早めの昼食を済ませ下山は今回のメインコース先の見えない長い急斜面を3つも超えていかなければならないというスリル満点ジェットコースターコースである。ただ、このコースはGW前の4月下旬頃なら山菜(わらび)摘みができるくらいのわらびの群生地でもある。
誰ひとり怪我することなく無事下山することができた後は、本日のお楽しみ大日影トンネル遊歩道を観光しながら勝沼ぶどう郷駅へと向かった。最後に、仕事が不規則勤務のためなかなか土曜日の会山行に参加できない僕にとっては、平日の魅力的な会山行は本当にありがたいなと思った・・・。おかげでとても充実した週休日を過ごすことができた。なかなか体験できないアトラクション山行を企画してくださったCL、同行したみなさんありがとうございました。


鋸尾根で下る「大岳山」
<コースタイム>
御嶽山駅9:40~御嶽山(神社)10:00~11:30大岳神社11:50~大岳山12:10~13:15鋸山~15:30奥多摩駅
東京都奥多摩に位置する大岳山(おおたけさん)は、標高1,266メートルを誇る名峰で、関東百名山や日本二百名山にも数えられる人気の登山スポットです。JR御嶽駅で下車し、ケーブルカーを利用して標高820メートルの御嶽山駅から登山を開始しました。なだらかな山道や岩場を越えて大岳山に登頂し、下山は鋸尾根を通って奥多摩駅まで歩くロングコースに挑みました。
御嶽山駅から土産物屋が並ぶ通り、山岳信仰の歴史が息づく宿坊街を抜けると、「武蔵御嶽神社」が鎮座しています。ここでは澄み切った空気と展望の良さに心が洗われるような感覚を覚えました。
神社から先はいよいよ本格的な登山道に入ります。針葉樹林に包まれた道はよく整備されており、比較的歩きやすいのが特徴です。しかし、「天狗の腰かけ杉」と呼ばれる奇妙な形をした大木や、「綾広(あやひろ)の滝」などの見どころも多く、飽きることはありません。山頂に近づくにつれて岩場や急な登りも現れ、程よい緊張感があり、登山の充実感をより一層高めてくれます。
「大岳山」という名前の由来は、そのまま「大きな岳」、すなわち霊山として古くから尊ばれてきたことにあるとされています。山頂近くには「大嶽神社奥宮」が祀られており、現在でも山岳信仰の名残を感じることができます。社の入口には、狛犬ではなく「オオカミ」の像が鎮座しているのも特徴的です。江戸時代には修験道の修行地としても知られていたという歴史に思いを馳せながら、慎重に岩場を登っていきました。
山頂に到着すると、南西方向には淡く富士山の姿が浮かび上がり、その雄大な景色にしばし見入ってしまいました。東京でこれほどの自然と絶景に出会えることに、深い感動を覚えました。
下山路の「鋸尾根」ルートは、なかなかの難所でした。その名の通り、尾根道はアップダウンの連続で、急な下降や木の根が張り出した箇所も多く、体力と集中力が試されます。それでも、よく踏まれた登山道と、木漏れ日が美しく差し込む森や風の中で、心癒される瞬間も多くありました。終盤の愛宕山付近は岩場が続き、このコース最大の難所といえる場所でしたが、最後まで気を抜かずに歩ききり、参加者全員が無事に奥多摩駅へ到着しました。長い行程を終えたあとは、大きな達成感に包まれました。
今回の登山は、歴史や信仰、自然、絶景、そして岩場のスリルといった、あらゆる要素が詰まった非常に充実した一日となりました。大岳山は、単なる登山という枠を超え、心に深く残る体験を与えてくれる特別な山であると、改めて実感しました。

FUJIYAMAツインテラス・御坂黒岳
<コースタイム> 河口湖駅9:30〜三ツ峠入口登山口9:50 〜 11:08旧御坂峠 〜 12:10黒岳 ~ 12:15御坂黒岳展望台 ~ 黒岳12:40 〜 13:00すずらん峠 〜 13:15破風山 〜 13:35 FUJIYAMAツインテラス 〜 13:45新道峠 ~ 15:14 河口湖自然生活館バス停
電車の連絡がよろしくないため4時起き必須だったのに、目が覚めたら5時半! やってしまった。横浜駅から河口湖行きのバスでワープしようと試みるもすでに予約は受け付けていないとわかり、頭がくらくらした。遅刻の旨の連絡を入れ河口湖駅から登山口までバスではなくタクシーにしていただいた。CL、SLともに優しく待っていてくださり感謝感激(本当に申し訳ありませんでした)。何とか予定より20分ほどの遅れで霧雨の中、登山スタート。
樹林帯なのでたいして濡れず、ひんやりとして気持ちがいい。静かな山を御坂峠まで一気に500メートルほど登る。小雨が白くけむるなか、しっとり水気を含んだ木々の緑や咲き残りのツツジが映える。稜線は風が少し冷たい。黒岳少し先の展望台からは、雲に隠れて富士山が黒いおなかの部分だけを見せていた。
お昼をすませ、下山開始。途中、タバコの吸い殻のような不思議な形のキノコに遭遇。後で調べたらキイロスッポンタケというそうだ。
FUJIYAMAツインテラスは、その名の通りすてきなテラスが2カ所あり、好天ならば富士山の絶景スポットであることは明らかだった。しかし今日は絶景の霧が一面に広がり、ひとけのないテラスは静謐の一言。心が落ち着いていいなあ。
その後はフタリシズカや草タチバナなどの楚々とした白い花々に迎えられつつ、すべりそうな急坂をジグザグに下り林道に出た。なかなか楽しく充実した山行で諦めずに参加してよかった。また行きたいコースでCL、SLのお二人に感謝でした。


鳥屋戸尾根で登る「蕎麦粒山」
<コースタイム>
9:00川乗橋バス停~11:30笙ノ岩山(昼食)12:00~13:00長尾山~14:00蕎麦粒山~15:20踊平~17:20川乗橋バス停
前日は激しい雨が降った。当日の天気予報は、まことにあやふやなもので、午前中に雨は上がるとも言い、午後からは晴れる、いや、また雨になるとも言う。まさに”テンデンばらばら”の空模様である。出発した横浜の空には、まだ細かい雨が落ちていたが、奥多摩駅に降り立つ頃には雲間から日が差していた。幸いにも、登山の始まりは明るい光に迎えられることとなった。
蕎麦粒山──その名は、まるで里山のように素朴で、どこか親しみ深い響きを持つ。しかし、実際には奥多摩の山々の中でもとりわけ奥深く、そう気軽に訪れることのできる山ではない。標高1472.9メートル。名前の由来には諸説あり、山の姿が蕎麦の粒のように丸く小さいからとも、あるいはかつてその中腹で蕎麦が栽培されていたからとも伝わる。いずれにしても、自然と人の営みの気配が、その名前の中に静かに息づいている。
今回は、鳥屋戸尾根から登るルートを選んだ。地図を開けばすぐにわかるが、この尾根は標高差にして約1000メートル、長く急な道のりである。行き交う登山者の姿も少なく、まさに静けさに包まれた山路だった。登り始めは杉の植林帯で、登山者の足を無言で試すような急登が続く。だが、標高を上げるに従って森の様相は変わり、やがてブナの大木が立ち並ぶようになる。空気は澄み、あたりには山の気配が濃く満ちてくる。木々の隙間からは、東京都と埼玉県の境に連なる長沢背陵の稜線が垣間見え、遠くには雲取山や七ツ石山の広がりも思い浮かぶ。
黙々と登ること数時間、ようやく岩混じりの頂に至る。蕎麦粒山の山頂は狭かった。東に目をやれば、川苔山へと続く防火帯の縦走路が延び、西側の木立の隙間からは、天目山や雲取山方面の稜線を遠く望むことができた。奥多摩から奥秩父へと続く長沢背陵の一角に、いま自分が立っているという実感が胸にしみた。
本来ならば、ここから川苔山を経て鳩ノ巣駅へと抜ける縦走を予定していた。しかし、空にはすでに積乱雲が立ち上がり、午後には雷雨の予報も出ていたため、無理はせず、踊平を経て林道に下り、川乗橋バス停へと早めに下山することにした。急ぎ足で林道を進んでいるうちに、案の定、激しい雨に襲われた。それでも、無事にバス停にたどり着き、帰路のバスに乗車することができた。
雨に濡れたブナの森の、長い尾根道を歩いたひとときは、静けさと潤いに満ちていて、忘れがたい時間となった。山の姿は一つとして同じではなく、晴れの日もあれば雨の日もある。けれど、そのすべてが、山という存在の一部なのだと、あらためて感じさせられた。同行された皆さん、本当にお疲れさまでした。

救助講習
<コースタイム> 京急逗子葉山駅南口8:00→京急逗子葉山駅バス停8:10⇒長柄交差点8:30→川久保交差点→阿倍倉山頂 講習①9:20→二子山途中の斜面 講習①の垂直場面10:40→上二子山12:00(昼食)12:45 講習②→南郷上ノ山公園 講習③13:45/15:17→長柄交差点→逗子・葉山駅16:30
今日は30度越えの予報、水を沢山持ってこの講習に臨んだ。しかし、からっとして風がそよそよ吹いて心地の良いこと。避暑地を歩いているような山行となった。
安部倉山に着くと、安部倉山保全の会の方に巡り合い、新しい「さくらテラス」の道を教えていただき、そちらの方を見に行く。今までは、やぶでいっぱいだったところに道ができ、富士山と江の島が望めた。春には桜が咲くとのこと。また春訪れたいと思った。
ここでは講習①を行った。フィックスロープを張る。切り立って通るのが危ない場合などガースヒッチとエイトノット、カラビナを用いて木と木の間にロープを張る。これを頼りに木と木の間を渡る。垂直方向の場合は、エイトノットで結び目を作る。
次に二子山に行く途中急な斜面があったので、ここでフィックスロープを張り実践練習をする。エイトノットを手の届く間隔で結び、それを頼りに下から登っていく。
二子山へ着き、昼食をとり、滑落者の引き上げの講習②を受ける。ガースヒッチでロープを固定し、ガルダ-ヒッチを用いて要救助者を救助する。要救助者は自らボーラインノットで自分の腰にロープを結びつける。救助者がロープを引くと、するすると要救助者が上がっていった。
南郷上ノ山公園の東屋で、応急処置の講習③をする。まずは、三角巾を使って腕を固定する方法、それから膝、足首を固定する方法を学ぶ。そのあと低体温症になった場合に、体を温める方法(濡れた服を脱がせるなど)と熱中症になった場合は、その逆で服を濡らして体を冷やす方法などを学ぶ。心肺蘇生法も参加者が順に行う。救急要請をする時は、自分の位置(座標)を知らせることが大事ということを聞き、その出し方も教えていただく。教わることが多く、直ぐできるように家でも練習が必要だと思った。



平標山・仙ノ倉山
<コースタイム> 登山口9:10→11:10 松手山→12:45平標山→13:00お花畑ベンチ(昼食)13:20→14:00 仙ノ倉山 14:15→15:00 平標山→15:35 平標山の家→16:35 登山口 → 17:20 バス停
東京発6:36のたにがわ401号で越後湯沢へ。駅からバスに乗って9時前に登山口到着。新幹線に乗れば越後の山も日帰り山行が可能な事を知りました。もう梅雨は明けたの?と思う程の快晴で登り始めから汗が噴き出ます。4合目の鉄塔まで上がると景観が良くなりお花もチラホラ出てきました。手前の松手山からは陽を遮るものがなく日傘を出しました。最後の登りを頑張ってどうにか平標の山頂へ。山頂は日差しが強く暑いので、仙ノ倉山へ15分程向かった所に風の通る涼しいベンチがある事を前回来た時に知っていたのでそこでお昼休憩を取りました。そこからはお花畑の中を仙ノ倉山まで進みます。仙ノ倉山の山頂は人もまばらで涼しくて快適でした。谷川岳方面も良く見えて気持ち良い山頂でした。そこから平標山に戻り、平標山の家を経由してバス停まで下山。タクシーを呼んで越後湯沢の駅まで戻り、駅近くの銭湯でさっぱりして新幹線で反省会をしながら戻ってきました。とても充実した山行となりました。ありがとうございました。