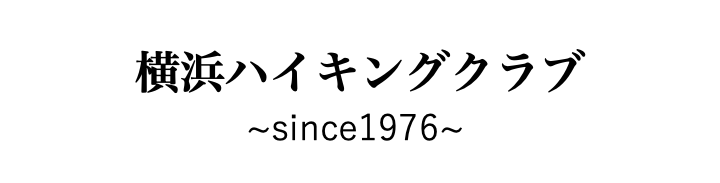丹沢山三峰ルート 4月29日(火) 晴れ
<参加者>(5名)
<コースタイム> 本厚木駅バス停7:55…三叉路バス停7:51→御殿森ノ頭8:42→高畑山9:23→本間の頭11:40(昼食)→円山木の頭12:33→太礼の頭12:59→丹沢山13:52→塔ノ岳15:33→大倉バス停18:13
前日は雨だったが、当日は予報通りGWらしい爽やかな晴れとなった。本厚木駅前のバス停に集合して宮ケ瀬行のバスに乗車し登山口まで進む。1日に20キロ近く歩くのは初めてだったので、最初は緊張気味だった。歩き出すと登山道は静かなブナ林で、オオルリやキビタキのさえずりに癒される。
序盤は緩やかな登りで、標識ごとに丹沢山までの距離が1キロずつ短くなるのが励みとなる。しかし緩やかな登りが続くことはなく、三峰の一角である本間の頭の手前からは急登が登場する。本丸の丹沢山前の登りは思いのほか長く「この1キロは長すぎる」など文句を言いながらも一歩ずつ前進していく。
丹沢山まで登りきるとブナは芽吹き前で深山の気候の厳しさを実感する。その分マメザクラが美しく咲き、下界では過ぎ去った短い春をもう一度楽しめた。楽しみしていた富士山は雲に隠れて姿をみせてくれなかった。そこは残念。
休憩後、一旦下って登り返して塔ノ岳を目指す。いつもは人がたくさんいる塔ノ岳山頂も15時半を過ぎると人はまばらだ。少し晴れ間が出て、富士山が半分だけ姿を見せてくれた。最後は苦手な大倉尾根の下り。一人だとほとほと嫌になるが今日はYHCのメンバーが一緒なこともあり、どうにかバス停まで降りられた。
こんなロングコースを歩く人ってどういう人なの?と思っていましたが、私もその一人になれました。しかし余裕を持って馬鹿尾根を降りられるようになるにはもう少し時間がかかるようです。CL及び参加のみなさん、どうもありがとうございました。

蛭ヶ岳 丹沢主脈 5月3日(土) 晴れ
<参加者>(4名)
<コースタイム> 焼山入口バス停7:40→焼山9:06→姫次11:00(昼食)→蛭ヶ岳山頂12:45→丹沢山山頂14:37→塔ノ岳山頂15:45→大倉バス停18:09
日帰りでの丹沢主脈・主稜縦走は、Sさんが実質継承し、今やYHCでは毎年の定番山行企画となっている。私も第1回・第2回の主稜縦走に参加したが、その後、コロナによる中断、日程等が合わず、ここ数年参加できずにいたが、今夏、北・南・中央アルプス、東北での縦走山行を計画しており、登山体力面での不安を払拭するためにも参戦を決めた。
最近、5時間程度の山歩きしかしていなかったことと、齢を重ねたこともあり、総歩行距離25㎞、累積標高上り下り2,300mはかなり厳しく、蛭ヶ岳山頂手前の木段で脚はほぼ限界となり、その後は何とか余力で下ってきたものの、踏破できた満足感は大きかった。また、久々に歩いた、蛭ヶ岳~塔ノ岳までに至る稜線歩きは眺望がとても素晴らしく丹沢の醍醐味だと思う。
アクセスに制約があるものの、丹沢主脈は北丹沢と表丹沢の両方を味わえる魅力的なコースである。ただ、総歩行距離、アップダウンの厳しさを考えると、日帰りだと誰にでもお勧めできるルートではないが、ある程度体力・自信がついたら、挑戦すると良いと思います。

愛鷹山 5月11日(日) 晴れ
<参加者>(10名)
<コースタイム> 十里木9:30→越前岳11:30(昼食)12:00→富士見峠14:20→黒岳14:35→愛鷹山登山口バス停15:00→御殿場駅
新緑、風のささやき、揺れる花々、鳥のさえずり、霞む駿河湾、
 眼前に広がる雄大な富士の山、その向こうに雪白き山、輝く白銀の
眼前に広がる雄大な富士の山、その向こうに雪白き山、輝く白銀の
 峰々、南アルプス・・・・・・・・・ビールが美味い!
峰々、南アルプス・・・・・・・・・ビールが美味い!
充実した山行であった。
中倉山・沢入山 5月23日(金)~24日(土) 曇り
<参加者>(4名)
<コースタイム>
1日目 舟石峠10:45~備前楯山11:30~舟石峠12:10
2日目 銅親水公園駐車場5:30~中倉山登山口6:30~中倉山8:30~沢入山9:30~オロ山11:00~沢入山12:50~中倉山13:40~銅親水公園駐車場15:50
今回の山行は、栃木県日光市足尾町付近の山々で、かつて日本有数の産銅地として栄えた足尾銅山の一部です。地下には今も広大な坑道跡や銅資源が眠っているとされます。明治時代に起きた足尾銅山鉱毒事件では、銅精錬所からでる亜硫酸ガスにより、周辺の山々の森林が破壊され、今でもその爪痕が見られます。
横浜から足利市駅へ向かい、レンタカーで銀山平キャンプ場に到着。そのまま「備前楯山」の登山口である「船石峠」へ移動し、登山を開始しました。備前楯山は標高1273mの低山で、登山道は穏やかで、丁度、ヤマツツジが咲く中を進み、曇り空ながら山頂からは足尾の町並みと、いまだに禿山のままの山々が一望できました。過去と現在が交錯するような、印象深い光景でした。下山後は銀山平キャンプ場にテントを設営し、反省会の後、早めに就寝しました。
2日目は早朝から中倉山(標高1520m)へ。登山口からは、樹林帯の急登が続き、稜線に出ると一気に視界が開け、間もなく山頂に到着します。頂上北側に足尾銅山の精錬所跡や煙害で荒廃した山々が見られ、南側には深い森に覆われた山々が連なり、歴史の傷跡と豊かな自然のコントラストが印象的でした。さらに進むと、「孤高のブナ」と呼ばれる一本のブナの木に出会います。煙害の被害を免れ、今も力強く立つその姿は、自然の語り部のようでした。中倉山の先、北アルプスのような雰囲気の荒れた稜線と狭い岩尾根を越えて、標高1704mの沢入山(そうりやま)に到着。ここからは皇海山や遠く日光白根山や谷川連峰の山々が見渡せ、素晴らしい展望が楽しめました。その後も稜線を進むと、枯れた木の根や笹藪のバリエーションルートとなり、シャクナゲの群生地の中に、最終目的地であるオロ山(標高1822m)のピークに到着。雄大な皇海山を眺め、満ち足りた気持ちで下山の途につきました。自然の美しさと歴史の重みを体感した、忘れがたい山旅でした。そして、行程・計画全体を通して、いくつものミッションをギリギリで攻めつつも、的確に対応してくれたCLの見事な指示・判断と緻密な準備にも感謝と感服を覚える山旅でした。